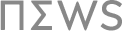 最新情報
最新情報- 2022.05.02 REPORT
-
Report 樋口裕康さん絵展で〝よいよい遊談〟
2022年4月22日、建築家の樋口裕康さんの絵展《何も要らない!?》の特別企画として、樋口さんとセイゴオによる「よいよい遊談」が行われました。この展覧会は、田中泯さんの拠点「plan-B」の40周年を記念して4月18日(月)~24日(日)の1週間にわたって開催されたものです。
plan-Bでの樋口さんの展覧会は、2019年12月に続いて今回が二度目となります。樋口さんは、1971年に象設計集団を設立し、世界各地の〝村〟を訪れ、それぞれの土地に根ざす歴史や物語を重視した建築を志向してきました。大病を機に、樋口さん自身の戦争の記憶や〝村〟というトポスへの思いを込めた圧巻の絵画を描きはじめました。
そんな樋口さんに展覧会の開催を提案し、作品づくりを応援し続けてきたのが田中泯さんと石原淋さん。コロナ禍のなか長らくクローズしていたplan-Bでしたが、ちょうど40周年を迎えるにあたり、左官職人の手によって内壁を土壁に塗り替えし、その〝新生plan-B〟でのイベント第1弾として樋口さんの再びの展覧会を開催されるにいたりました。
セイゴオもまた泯さんを通じて、樋口さんの絵に込められた「いのち」の「かたち」や、溢れ出る物語世界と色彩に触れて共感し、2019年の展覧会でも樋口さんとのトークに応じています。今回の展覧会に先立って、泯さんから樋口さんの新しい作品を見せられたセイゴオはさらに驚嘆しました。色彩が封印されて墨一色となり、樋口さんのおいたちや〝村〟の記憶がさらに緻密に輻輳的に描きこまれたものとなっていたのです。もちろん、二度目のトークも二つ返事でお引き受けしました。

ひさびさにplan-Bをおとずれたセイゴオを泯さんがお出迎え。なぜかよく似たキャップをかぶっているので見分けがつかないが、左が泯さん、右がセイゴオ。塗り直したばかりの土壁に圧巻の樋口さんの作品が展示されている。

改めて樋口さんの作品を一点一点味わうセイゴオ。樋口さんの作品は、横長の紙にまるで絵巻のようにいくつもの時間を重ねるように描かれている。折々筆をもって戯画に遊んできたセイゴオ、樋口さんが墨をつかって「かたち」を描きながらどう「白」を塗り残しているのかに興味津々のようす。

開演前、控室では早くも樋口さんと本番さながらの〝よいよい遊談〟が始まる(樋口さんもお揃いのようなキャップをかぶっている)。セイゴオが見ているのは、樋口さんが泯さんのダンス公演《村のドン・キホーテ》をドローイングした画帖。「こんなふうに舞台を描いたドローイングはない。最高傑作」と、セイゴオは大絶賛。

樋口さんの渾身の作品たちに囲まれながら遊談が始まる。よく似たキャップをかぶったままの樋口さんとセイゴオが、マスクで満場のお客様たちを相手に妙味のある対話を繰り広げる。
セイゴオ:どうして今回は墨色だけの作品に?
樋口:多様な〝生きもの〟を描くためにあえて墨一色でやってみようと思った。〝かすれ〟や〝にじみ〟もあえて使わないようにした。実際に筆をもって描いていくと、ずっと白と黒の境界のせめぎあいのような感じだった。墨をつかいながら、目では(塗り残されている)「白」を見ながら描いていく。やっているとヘンになっていく感じがした。
松岡:その「白」を見ながら墨で描いていく感覚はわかる。ぼくは子どものころから相撲文字や歌舞伎文字に憧れて、自分の名前を陰刻のハンコのように白く塗り残して書くということをやっていた。長じてからはマラルメなどの文字反転の感覚に憧れた。

セイゴオは、なかでもこの写真の右に写っている木の根の作品に驚いたと言う。樋口さんは、この絵を描いたことがきっかけで、今回の作品群が生まれていったと語った。
樋口:こうやって展示された自分の絵を見ると、自分でも説明がつかないこと、いままでにない〝世界〟があらわれているように思う。絵が自分から離れて生きているみたい。
セイゴオ:もともと絵でも文字でも筆記具をもって描くときは、自分でその生まれつつある文字や線を見ることができない(自分の手が遮蔽してしまう)。踊りもそういうものではないか。でもその「見えない」ところからこそ文化が生まれ、文化が生きる。
樋口:うまいこというね(笑)。
セイゴオ:人間の記憶にもそういうところがある。3歳くらいまでの幼児の頃の記憶がない。赤ちゃんがしきりに虚空で手を動かしている様子をじっと観察したことがある。そのとき、赤ちゃんはじつは自分の手で「いないいないばあ」をして遊んでいるのではないかと気づいた。そこから、「いないいないばあ」こそが世界の表現の根源にあることだと考えるようになった。樋口さんの絵にもこの「いないいないばあ」が満ちている。
樋口:そう言ってもらえてうれしい。みんな「かたち」あるものが知識だと思っているが、本当にそうなのか。たとえばウイルスの「かたち」なんて誰もわからない。だったら自由に描けばいい。顔のあるウイルスがいたっていい。何億年も生きてきたウイルスたちはもっと自由なはずだ。

二人の背景にある屏風仕立ての作品だけは極彩色の作品。ロシアによるウクライナ侵攻に「身体が引っ張られて」、ジェノサイドへの怒りや広島の原爆や沖縄戦などの日本の戦争の記憶も込めて新たに描いたもの。
セイゴオ:泯さんも樋口さんもぼくも、みんな「戦時中」に生まれた。そのことを今まで一度も忘れたことがない。ぼくたちはいつでも「有事」のなかにいる。
樋口:「時」というものは、過去から未来へと進んでいくものだけではない。「場所」にはたくさんの「時」が集まっていっしょになって動いている。だから昔のことをちゃんと見たいと思う。その場所の「時」を表現し、自分もその一部になりたい、その場所の「生きもの」になりたい。
セイゴオ:古代の人びとが描いた絵はことごとく「創世記」になっている。世界というものがどうつくられてきたのかということが込められている。樋口さんの絵もまさにそういうものではないか。
樋口:自分でもそう思う。いつも部分的なラフスケッチはたくさんしているが、「創世記」の気分になると、ちょっとは〝稽古〟しながら描くようになった。
セイゴオ:よくわかる。何が世界の「地」で何が「図」なのかを、ちゃんと描き分けている。

対談の締めくくりに、樋口さんは大きな声で「戦争反対」を訴えた。メディアも世のなかも戦争の解釈や解説にかまけているばかりで「反対」を声にしないことに憤りを覚えていると語った。

セイゴオは、樋口さんによる《村のドン・キホーテ》のドローイングを絶賛を込めて紹介。後ろでは二人の対談を聞いてすっかり体が騒いでいる泯さんが(マスクをしていてわかりにくいが)微笑んでいる。

キャップをかぶった三兄弟のような泯さん、樋口さん、セイゴオ。樋口さんの手にしているのは杖代わりの2本の竹。展覧会直前にギックリ腰を患い、泯さんのアドバイスでこうして2本の杖を突いているという。満身創痍の樋口さんだが、現代社会や戦争や建築界に対するラディカルな批判精神が縦横無尽に爆ぜていた。泯さんはこの翌日、昼夜二回のダンス公演を行い、その一部始終を樋口さんが筆を構えて見通していた。
レポート:太田香保
写真:寺平賢司
